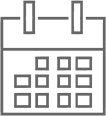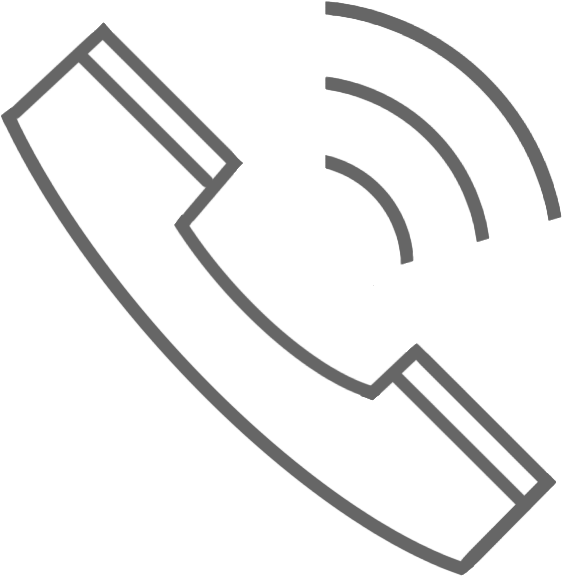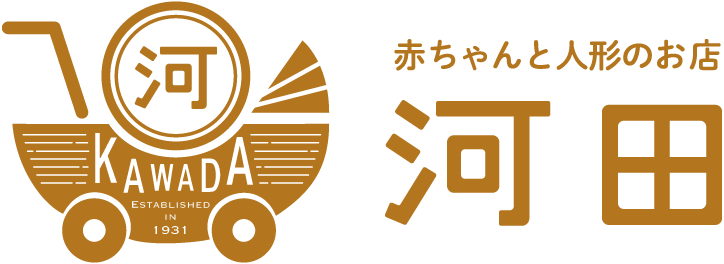商品記事
2023.04.17更新

こちらは
「兜(かぶと)」についての記事です
南北朝時代の【大鎧】国宝模写が揃ってます!
端午の節句をお祝いする鎧兜
そんな鎧兜を選ぶ際、店内でも一段と目を引く一文字
【国宝模写】
全国の寺社に所蔵された国宝を模写した重厚感ある鎧兜。
大きくなったらお子様と一緒に実物を見に旅行に行ってみるのも楽しいですよね♪
今回はその中でも特に人気の3種類をご紹介いたします!
赤糸威鎧(菊金物)
国宝・赤糸威鎧(菊金物)(きくかなもの)は、大袖には籬(まがき)に八重菊を象った金具の上に
「一」の字の飾金物(かざりかなもの)が施されているため、「菊一文字の鎧」と呼ばれています。
また兜にも同様に菊一文字の飾金物があることから、「菊一文字の兜」の異名を持っているのです。
鎧の形状は、典型的な鎌倉後期における大鎧の特徴を有する物。
これに、余すところがないような形で装飾されている菊籬(きくがき)を模した金物に見る精巧な透かし彫りは、
鎌倉時代における金工芸術の特色をよく表しているのです。この赤糸威鎧(菊金物)は現存する大鎧における装飾金物の絢爛豪華さという点で、
「春日大社」所蔵の赤糸威鎧「竹雀虎金物」(たけすずめとらかなもの)と並び称される逸品です。
現在は、青森県八戸市にある「櫛引八幡宮」(くしひきはちまんぐう)の所蔵となっています。

赤糸威鎧(竹雀虎金物)
奈良県・春日大社所蔵の国宝・赤糸威鎧(竹雀虎金物)は、鮮やかな赤い威毛と精巧な金物が印象的な大鎧。
兜には竹と雀を基調とした飾金物が施され、大袖には大きな虎の金物が添えられています。
また兜前面の鍬形は長さ48.5㎝で、上端の幅は21㎝の特大サイズ。
社伝では源義経によって奉納されたとされていますが、製作様式などを鑑みると、鎌倉時代後期の作と推定されます。
この赤糸威鎧(竹雀虎金物)も上記2つの赤糸威鎧と同様に、札に多くの装飾用金物を用い、大袖にも竹と虎の金物を配して重量が大きく、
柔軟性にもかけていることから、実用ではなく、奉納用として作られた1領であると言われています。

白糸威褄取鎧
青森県・八戸市にある櫛引八幡宮所蔵の国宝「白糸威褄取鎧(しろいとおどしつまどりよろい)は南北朝時代を代表する大鎧。
白糸を卯の花に見立てて「卯の花威」(うのはなおどし)とも呼ばれていました。
外側から紅糸、萌黄糸、黄糸、薄紫糸、紫糸の順で褄取り(つまどり:袖や草摺の端を斜めに地糸とは異なる糸でおどすこと)を施したことで、
地糸である白糸の威毛を一段と引き立たせています。現在残っている褄取部分は後年に補修されたものですが、
均整がとれた全体の形状もあいまって、製作当時の気品に満ちた様子を偲ばせる1領です。
この大鎧は、南朝の武将として活躍した「南部信光」が甲斐の国を平定した報償として後村上天皇から与えられたと言われるもの。
その後、信光の子が櫛引八幡宮に秋田合戦の戦勝祈願をし、勝利を収めた御礼として奉納しました。

ゆっくりご覧になって味わっていってみてくださいね!