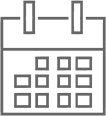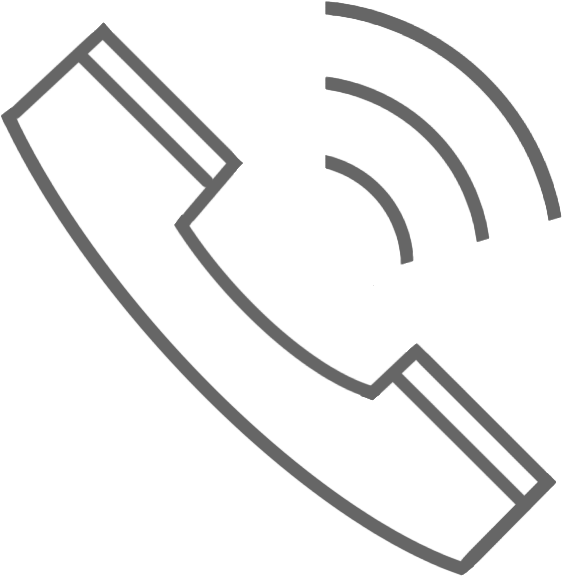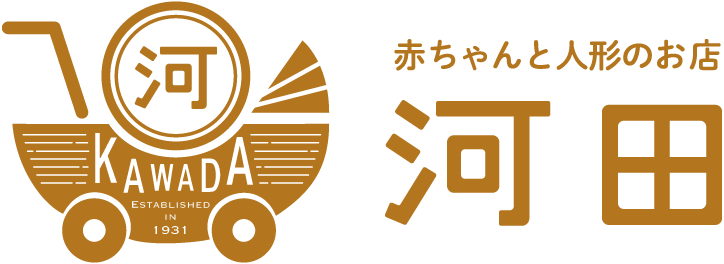商品記事
2022.04.19更新
兜の立物【五月人形】
五月人形を選ばれる際にやはり皆さんが気になさるのが兜の「立物(たてもの)」

今回はその立物についてお話させていただきますね!
まず、立物とは…
「眉庇・目庇(まびさし)」や「鉢(鉢)」に立てることで、
兜を装飾すると共に、着用者の威厳を示して存在感を誇示するものの総称です。
デザインは動物、植物や器物などをモチーフにした立物や、信仰に根差して日や月をかたどった立物がありました。
素材も鉄、鋼、金、銀、真鍮、木材、舘、獣の角、牙、皮革など様々でした。
立物は、立てる位置によって「前立(まえだて)」、「頭立(ずだて)」、「脇立(わきだて)」、「後立(うしろだて)」に分かれます。
これらは自己顕示のためや、戦場における味方同士の目印としても用いられました。
立物の起源は、古墳に副葬品として埋葬された兜まで遡るといわれています。
代表的なものは野球帽に似た形をした「眉庇付冑(まびさしつきかぶと)」です。
これは後頭部に「伏板(ふせいた)」と呼ばれる円盤状の鉄板を乗せ、頭頂部の伏板の上には
「伏鉢(ふせばち)」、「受鉢(うけばち)」と呼ばれる2つの半球形金具を
「菅」と呼ばれる筒状金具で接続して立鼓状に組み立てたものが乗せられています。
眉庇付冑は、5世紀中頃から6世紀にかけて用いられたとされています。
中世における主流は、前立の一種「鍬形(くわがた)」です。
もっとも中世初期においては、立物(鍬形)は普遍的なものではなく、軍を率いて指揮を執る大将などの身分を示すための意義を持つものでした。
平安時代末期ごろから、龍が用いられるようになり、その後、南北朝時代から戦国時代にかけて、日本各地で力を付けた新興勢力が台頭してくると、
それぞれの武将に様々な立物が現れてきました。
南北朝時代の初期に使われたのは、日輪や月輪(がちりん)です。
日輪は「生命」のシンボル、月輪は「不死と再生」のシンボルと考えられていたといわれています。
その他、獅子・鬼・高角・角・鏡・剣・扇・植物・動物・鳥・魚貝・虫・神仏・三形(さんぎょう)・
家紋・輪など、様々なものをモチーフとした立物が作られるようになりました。
兜に立物を装飾することが一般的になった戦国時代以降、個人的な軍備として用いられてきましたが、江戸時代に入り集団的な統一された軍層に移行されてからは、
他家との識別を明確にすることに目的が変化していきました。
「鍬形」の種類
兜の立物で、もっとも一般的だったのは鍬形(くわがた)です。
鍬形の原型は、古代の「鍬」にあるといわれています。
主な鍬形の種類について紹介します。

【鉄鍬形(てつくわがた)】
雲龍文や獅噛文(しがみもん)の象嵌を施し、鍬形台と一体に作られた鉄製の鍬形。
鍬形に権威を持たせて平安から鎌倉時代に用いられていました。
代表的なものとして重要文化財「雲龍文象嵌鉄鍬形(うんりゅうもんぞうがんてつくわがた)」:長野県清水寺所蔵
があります。
【長鍬形(ながくわがた)】

細長い鍬形。鎌倉時代後期に流行し、その後、鍬形と鍬形台が分かれるようになりました。
代表的なものとして、国宝「紅糸縅鎧」(梅鷲金物)の兜の鍬形(奈良県春日大社所蔵)があります。
【大鍬形(おおくわがた)】

八双の先端を外側に細長く伸ばした大鍬形。南北朝時代に祭礼に用いられたといわれています。
代表的な物に高知県宿毛市の山田八幡宮が所蔵し宿毛歴史館で保管している「日本一の大鍬形」があります。
【木葉鍬形(このはくわがた)】
鍬形全体を木の葉に似せて作られたものです。室町時代後期に用いられました。
代表的なものに重要文化財「色々縅腹巻」の兜の鍬形(島根県佐太神社所蔵)があります。
【三鍬形(みつくわがた)】
中央に剣を立てたものと左右の鍬形を合わせて三鍬形。室町時代に流行しました。
代表的なものに、重要文化財「色々縅胴丸」の兜の鍬形(鹿児島県鹿児島神社所蔵)があります。
立物のデザインや大きさによって兜の雰囲気はかなり変わります。
店頭にて実際の兜と立物、屏風をご覧になり、お気に入りの一点を見つけてみてくださいね!